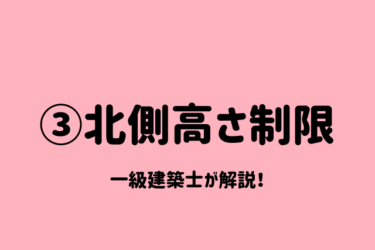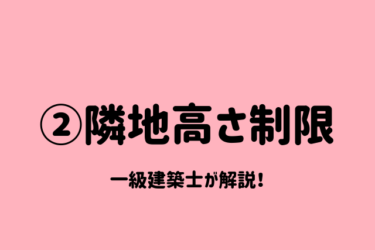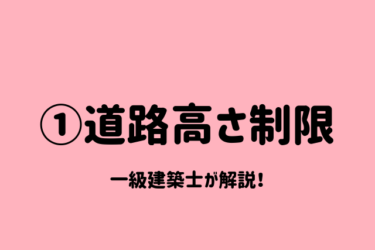こんにちは。恵比寿不動産です。
一級建築士兼宅建士がわかりやすく解説していきます。
今回は、
・防火地域
・準防火地域
です。
これらの地域に該当したら
建築費がアップします。
理由は、簡単にいってしまうと
燃えにくい建物にしないといけないからです。
では、見ていきましょう!

・建築コストがアップしてしまう理由が知りたい人
【定義】防火地域、準防火地域とは?
市街地における火災の危険性を防除するため定める地域(都市計画法第9条第20項)
ってことです。
じゃあ、防火地域や準防火地域に建てるとき、具体的にどうしたらいいいのでしょうか?
防火地域内に建てるとき
規模によって変わってきます。(建築基準法第61条より)
| ・階数が3以上
・延べ面積が100㎡超え |
耐火建築物 |
| ・その他 | 耐火建築物又は準耐火建築物 |
つまり、
・コンクリート
・鉄骨
・特殊な仕様の木造
など。
こういう値段の高い構造にしないといけないのです。
準防火地域内に建てるとき
こちらも規模によって変わってきます。(建築基準法第62条より)
| ・地階を除く階数が4以上
・延べ面積が1500㎡超え |
耐火建築物 |
| ・延べ面積が500㎡を超え、1500㎡以下 | 耐火建築物又は、準耐火建築物 |
| ・地階を除く階数が3 | 耐火建築物、準耐火建築物又は政令で定める基準に適合する建築物 |
防火地域よりは緩い規定になっています。
ここで、あれ?普通の2階建ての住宅は該当しないじゃん!
コンクリートや鉄骨で作らなくていいじゃん!
安くなる!やった!
って思うかもしれません。
確かにコンクリートや鉄骨で作る必要はありません。
しかし、ある措置をしなければなりません。
「外壁」、「軒裏」、「屋根」、「開口部」を燃えにくくしないとダメ
根拠は、以下の通りです。
(一部抜粋して載せておきます。)
建築基準法第62条第2項
準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
建築基準法第63条
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して適合したものとしなければならない。
建築基準法第64条
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備(遮炎性能を有するもの)を設けらければならない。
つまり、
・外壁→防火構造
・軒裏→防火構造
・屋根→不燃材料
・開口部→防火設備
という性能を持った材料を使って建物を燃えにくくします。
一戸建ての住宅でもこういった材料を使うので
コストアップになってしますのです。
さいごに
防火地域、準防火地域内の建築物は、
・燃えにくい構造
・燃えにくい材料
としなければならないのでコストが高くなってしまいます。
コストを極力抑えたいあなたは、
抑えておきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。